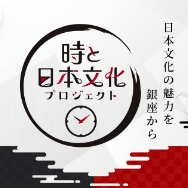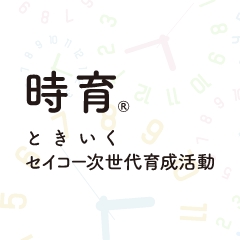セイコーのサステナビリティ
取材・執筆:淺野義弘
取材・編集:友光だんご(Huuuu)
撮影:本永創太
- #
自動車は私たちの社会になくてはならない存在です。食卓に並ぶ食材や日用品、建設現場の資材、そして通勤や営業で移動するビジネスパーソンまで、さまざまなものや人が”働く車”によって運ばれています。
しかし便利な車社会の裏側で、思わぬ事故やトラブルのニュースを目にする機会も増えてきました。物流や旅客事業を中心に、勤務時間の増大やそれに伴うハードな労働環境は大きな課題になっています。安心して運転できる環境をどう守るかは、これからの社会や多くの職場で考えるべき重要なテーマと言えるでしょう。

こうした課題の解決に挑んでいるのが、セイコーソリューションズの「Mobility+(モビリティプラス)」。アルコールチェックとデジタルキーや運転日報の自動作成など、車両管理に伴う業務を簡単かつ確実に行えるサービスとして、企業や自治体への導入が進んでいます。
ドライバーも車両管理の担当者も「安心・安全」に利用できるMobility+。このサービスがセイコーグループから生まれた背景や、現場で果たす役割について開発チームの皆さんにお話を伺いました。

お話を伺ったセイコーソリューションズの4名。左から並木敦子さん、飯島俊太さん、石動泰平さん、程田雅道さん。
デジタル制御システムで、運転前の安全管理を徹底
まずはMobility+の象徴的な機能である「デジタルキー」と「アルコールインターロック」を実演いただきました。

システムを搭載した車両に乗り込む際は、スマートフォンからMobility+アプリを開き、画面上のボタンをタップしてドアロックを解除します。
エンジンを始動する際には、画面の案内に従ってアルコールチェックを選択。


システムと連動したアルコールチェッカーに息を吹きかけると、記録用に使用者の顔も撮影しながら計測が行われます。その後、アルコール含有量が規定値以下であることが確認されると、はじめてエンジンを始動できる仕様になっています。
物理的な鍵の受け渡しが不要になるデジタルキーと、アルコールが検出された場合にはエンジンが始動しないアルコールインターロック。この二つの仕組みによって「鍵をうっかりなくしてしまう」「アルコールチェックを忘れてしまう」といった人為的なミスをシステムで予防し、安全な車両運用を実現しているのです。

このほかにも、Mobility+には車両管理を支えるさまざまな機能が備わっています。たとえば運転日報の自動作成では、これまで手書きで行っていた記録作業が自動化され、オンラインでも確認できるようになりました。また、車両予約機能やリアルタイム位置情報の共有によって、社用車の予約や運用の効率化にも役立っています。
セイコーの小型で堅牢な通信機器が、車社会の進化を支える
セイコーが、なぜMobility+のような車両管理システムを開発することになったのでしょうか。その歩みや背景について、開発チームの皆さんにお話を伺いました。
まずはセイコーにおける車両管理システムの歴史について教えてください。

飯島俊太さん(モバイル・IoTソリューション本部 モバイル・IoT技術統括部 モバイル・IoT技術3部 モバイル・IoT技術5課 担当課長)。プロジェクトリーダーとハードの設計、システム開発を担当。
飯島さん:セイコーは、およそ20年以上前から車載用通信機の開発に取り組んできました。もともとPHSや3G、LTEなどに対応する通信機器を手がけてきた経験があり、そこから発展する形で、遠隔通信やドライブレコーダーを活用した「テレマティクス(車両と情報通信技術を組み合わせた分野)事業」へと広がっていったのです。
程田さん:Mobility+の原型となるのは、セイコーの法人向け安全運転支援サービス「Drive Cloud+(ドライブクラウドプラス)」です。安全運転指導や車両管理を効率化し、運行管理者の管理負荷軽減と安全運転推進を実現しています。さらに、新たなアルコールインターロック機能を加える事で、Mobility+が誕生いたしました。

程田雅道さん(モバイル・IoT技術統括部 モバイル・IoTシステム部 モバイル・IoTシステム課 課長)。サーバー運用やスマートフォン連携を担当。
機器開発にもセイコーならではの強みがあるのでしょうか?
飯島さん:Mobility+は制御用のハードウェアを車両に取り付けて使います。自動車に搭載される装置は、一般的な電子機器に比べてはるかに過酷な環境で使用されます。真夏の車内は非常に高温になり、冬には氷点下まで冷え込むこともありますし、常に振動や衝撃も加わります。こうした厳しい車載空間で確実に使えるためには、高い耐久性が不可欠です。
セイコーソリューションズには、時計や電子機器の開発で培った精密な設計技術や無線通信術、品質評価のノウハウがあります。これらの経験を活かすことで、車載用デバイスも高い信頼性を持ってご利用いただけるサービスになりました。また、限られた車内スペースに収まるコンパクトな設計にも、精密機械を小型化してきた時計づくりの経験が活きています。
高い信頼性とコンパクトさは、時計にも車載機器にも欠かせない要素ですね。
飯島さん:おっしゃるとおりです。また、自動車業界との長年の協力関係があったからこそ、さまざまなメーカーの車両でもスムーズに導入できる体制を築くことができました。こうした経験と実績は、セイコーならではの強みだと自負しています。
アルコールチェックの義務化は、働き方が変わる大きな契機

並木敦子さん(モバイル・IoTソリューション本部 モバイル・IoT営業第2統括部 テレマティクス推進課 課長)。Mobility+のサービス企画を担当。

Mobility+最大の特徴である、アルコールインターロックの開発経緯を教えてください。
並木さん:個人の判断やアナログな仕組みに頼っていると、どうしても“うっかり忘れてしまう”ことが避けられません。もし後から「実施されていなかった」と判明すれば、事業者の信用問題にも直結します。
Mobility+は、こうしたリスクをシステムで解決するソリューションとして開発されました。現在は、コンプライアンス意識の高い企業や自治体を中心に多くの問い合わせが来ています。
程田さん:Mobility+はクラウドサーバに接続し、運転日報や運行記録を自動で残すことができるのも大きな特徴です。運転者だけでなく、運行管理側の業務負担も大きく軽減できる仕組みになっています。
開発で苦労した点について教えてください。
石動さん:まずはアルコールチェッカーの仕様を理解し、当社のデバイスと正確に連携できるかを徹底的に検証しました。設計検証、テストを何度も繰り返し、現場で実際に使う人の立場から「どこが使いづらいか」「どこに課題があるか」を丁寧にヒアリングしながら改良を重ねていきました。使いやすさを重視したシステムとして、通信処理のスピードにもこだわっています。

石動泰平さん(モバイル・IoTソリューション本部 モバイル・IoT技術統括部 モバイル・IoT技術2部 モバイル・IoT技術2課 担当課長)。デバイス開発を担当。
飯島さん:車両に取り付けるハードウェアですから、低電力で安定して動くことにもこだわりました。また、さまざまな車種で使われるため、私たちのデバイスが原因で車両の動作に影響が出ることがあってもいけません。初めて導入する車種の場合は、必ずお客様のもとに伺い、動作確認・検証を行うようにしています。
現場の声をもとに、安心して使えるサービスに育ててきたのですね。
飯島さん:システムの設計から取り付け、アフターサポートまで一貫して対応できるのも、セイコーグループならではの強みです。Mobility+は7月30日より提供を開始しますが、今後も現場の声を反映させながら、サービスをさらに進化・アップデートさせていきたいと考えています。
社会の変化に技術で応える

自動車業界の変化は、テクノロジーの進化だけでなく、私たちの働き方や現場の安全意識にも大きな影響を与えています。とくに業務で車を使う現場では、法令順守や事故防止、効率的な管理など、働く人と管理する人の双方が課題に向き合う時代になりました。
Mobility+は、そうした時代のニーズに応えようとする現場の声から生まれました。人を思いやる細やかな心遣いと、長年にわたり培ってきた「安心を生む技術」。その両輪に支えられながら、インクルーシブな社会インフラの構築を目指すMobility+の挑戦はこれからも続いていきます。
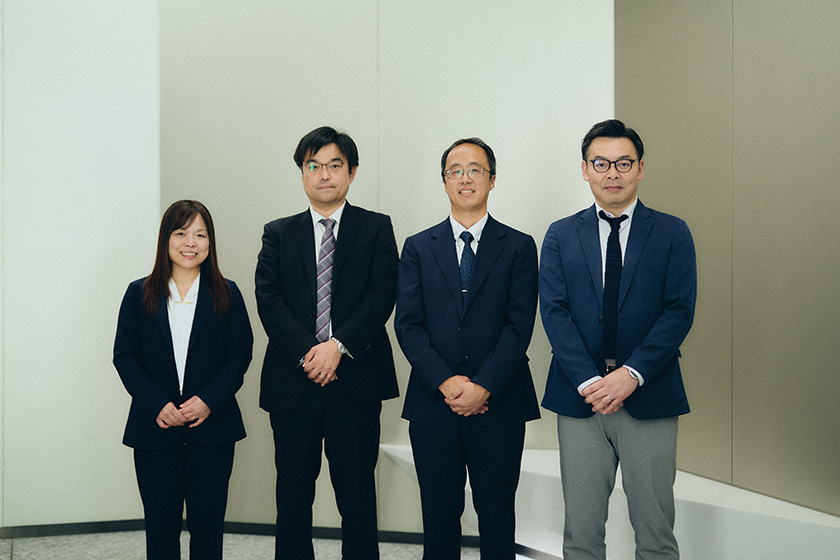
おすすめの記事
Pick Up Contents
合わせて読みたい関連記事
About
サステナブル・ストーリーとは、持続可能な社会に向けて、
セイコーだからできるサステナブルな活動を発信していく
Webメディアです。
- ホーム
- サステナビリティ
- サステナブル・ストーリー
- 働く車を見守る新たなインフラ。セイコーのMobility+は「安心・安全」を仕組みに変えていく