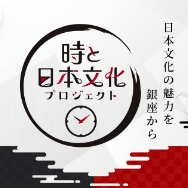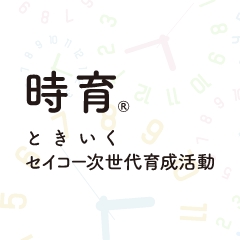セイコーのサステナビリティ
取材・文 遠藤光太
写真 落合直哉
- #
2024年元日に発生した能登半島地震。マグニチュード7.6、最大震度7の大地震は、住宅倒壊、住宅火災、地盤災害、津波発生など石川県能登地方を中心に甚大な被害をもたらし、多くの妊産婦が入院する七尾市の恵寿総合病院にも直撃しました。その影響で産科病棟が断水状態に陥り、本館の内視鏡センターへの緊急避難が必要となり、さらには妊婦の状態をリアルタイムで監視するセントラルシステムが使えない非常事態が発生しました。
そんな年始の混乱状況において能登地方のお産を守ったのが、分娩監視システム「emona(エモナ)」です。「emona」は持ち運びが可能で、災害時や搬送中などどんな状況下でも母子の健康状態を確認できるシステムです。能登半島地震による災害に見舞われた恵寿総合病院においても活躍しました。
「emona」の開発には、セイコーグループの関連会社、CSMソリューションが携わっています。震災発生時にセイコーの医療ソリューションはどのような貢献を果たしたのでしょうか。震災当時の病院内での対応、「emona」開発秘話など多岐にわたり、関係者のみなさんにお話を伺いました。
※院内取材のため、インタビュー中はマスクをご着用いただきました

能登半島の特徴的な地形を右手の親指を少し曲げることで表現した「能登ポーズ」をとる、左からトーイツ株式会社 執行役員CTO 研究開発部 マネージャ 内田史景さん、株式会社CSMソリューション 取締役・副社長執行役員 市川剛司さん、恵寿総合病院 産科科長・臨床研修センター長 新井隆成さん、執行役員 柴﨑永人さん、営業統括部 ソリューション営業部課長 小原琢哉さん(ともに株式会社CSMソリューション)
写真 落合直哉
分娩監視装置とセントラルモニタが融合。分娩監視システム「emona」とは

分娩監視システム「emona」について説明する開発メーカー・トーイツの内田さん。医療の現状において、「臨床的価値」「ユーザー生産性」にプラスして、3軸目の「社会的価値」の重要性を説きました
写真 落合直哉
分娩監視システム「emona」は、胎児の状態を計測する分娩監視装置「emona CTG」と、遠隔にある複数台の分娩監視装置のデータを集約し、一か所で監視できるセントラルモニタ「emona CENTRAL」で構成されています。システムにバッテリーや無線LAN、メモリー機能を内蔵することで分娩監視装置の持ち運びを可能にし、情報のクラウド化によってどこでも妊婦の情報が確認できるようになりました。救急車内や災害現場などの遠隔地や緊急事態でも、セントラルモニタで母子の健康状態をリアルタイムで監視できる点が最大の特徴です。「emona」の機能性や開発への想いを産科、婦人科、新生児医療機器メーカーであるトーイツの担当者・内田さんに聞きました。
分娩監視システム「emona」について教えてください。
内田:「emona」は、トーイツがCSMソリューションさんの協力を得て提供している分娩監視システムです。従来は、分娩監視装置とセントラルモニタを別々に開発していましたが、それぞれを改善するだけでは不十分な領域が生じることが分かってきました。そこで、分娩監視装置とセントラルモニタを融合させ、「分娩監視システム」という包括的な位置づけにすることにより、医療現場のより多くのニーズに応えることが可能になりました。
機能性に加えて、デザイン性についても評判が高く、2023年にはグッドデザイン賞も受賞しています。今までの知見を活かして新たな社会課題の解決に結びつけた点をご評価いただいたと理解しています。
元々は別のシステムをあえて融合することで、より多くのニーズに応えることができたのですね。現在、さまざまな医療問題が深刻化していますが、多様化するニーズに応えるためにトーイツが取り組んでいることを教えてください。
内田:トーイツはこれまで機器やシステムの精度を上げる「臨床的価値」と使用する人の手間を削減する「ユーザー生産性」の2軸を重視してきました。
しかし、昨今は医師不足、災害対応、出生率減少など、以前には考えられない規模で医療問題の深刻化が進んでいます。そこでトーイツでは、数年前から3軸目として「社会的価値」を追加して製品開発に取り組んでいます。製品の性能を上げるだけでなく、より高い次元で社会課題を解決することを目指しています。
そのような動きの中で、今回「emona」の開発に取り組みました。
元日に能登半島地震が発生。不安と恐怖、絶望の中での対応――

震災前から周産期医療において人手不足だった能登地方だけに、恵寿総合病院の新井先生は「できるだけ早く平時の状態に戻すこと」に奔走したと当時を語ってくれました
写真 落合直哉
年始の能登、お産を控えた多くの妊婦さんが利用する恵寿総合病院を襲った巨大地震。突如として大混乱に陥った現場では何が起こっていたのでしょうか。切迫する被災地の医療現場の状況を、恵寿総合病院の新井先生に詳しく語っていただきました。
2024年1月1日に能登半島地震が発生しました。新井先生が勤務する恵寿総合病院では、どのような問題に直面しましたか?
新井:非常に大きな災害で、能登半島に位置している恵寿総合病院も甚大な被害を受けました。まず断水や水漏れが生じて、産科病棟が使用不能になりました。胎児心拍数モニタリングや監視装置を含めて、ハード面が通常通りに使えない非常事態でしたね。また、私たち医療従事者自身も被災者であるため、医療に携わる人手も明らかに不足していました。しかし、被災者の生活を支えるためにも、医療の継続が最重要課題です。そのため、知恵を出し合って非常事態に向き合いました。
使用できる医療機器を活用しながら、超急性期・急性期※1の患者さんから対応を進めるという切迫した状況でしたね。一刻も早く平時の状況に近づけるために、1時間ごと、30分ごと、必要であればそれこそ1分ごとに話し合いをしていました。院外にも要望を挙げて、とにかく早く医療を継続できる体制を作ろうと奔走していました。
産科病棟が使用不能になった際、多くの妊産婦の方が病棟にいました。具体的にどんな対応をされたのでしょうか?
新井:妊産婦さん、周産期医療※2にかかわる医療従事者ともに、不安、恐怖や絶望を覚えるかなり深刻な状況でしたが、病院としての対応は非常に迅速に行えたことが救いでした。産科病棟が使用できなくなった後、免震構造に守られていた本館に移動しました。周産期医療はお産など母子の命に直接的に関わるだけに、緊急的な対応が非常に多い領域です。本館の中でそうした緊急対応にもっとも適した場所は、内視鏡センターです。そのため、周産期医療チームを本館の内視鏡センターに移して対応しました。
二次的な医療インフラを備えられていたことで、周産期医療を継続できる見通しが立ったことは不幸中の幸いだったと言えます。しかし、妊婦さんの状態をリアルタイムで監視できるセントラルモニタが使用できなくなったことの影響は大きく、一刻も早く回復させる必要がありました。そうした危機的な状況において、緊急の要望を出したことで「emona」の設置につながりました。
※1 超急性期:発症・受傷や術後直後(数時間以内)の状態
急性期:発症・受傷や入院から14日程度の期間
※2 周産期医療:妊娠22週から出生後7日未満までの周産期のケアや支援を重視した医療
4営業日でセントラルモニタリングが可能な状況を構築

慢性的に人手不足な能登地方では、周産期医療において遠隔でもリアルタイムで妊婦さんの情報を集約できるセントラルモニタリングが不可欠と言えます
写真 落合直哉
セントラルモニタリングは、周産期医療においてどのくらい重要なのでしょうか?
新井:周産期医療の環境面をしっかりと支えるうえで、妊婦さんの状態を離れた場所からでもリアルタイムで監視できるセントラルモニタリングは不可欠だと言えます。なぜなら、周産期医療は全国の多くの地域で慢性的に人手が不足している領域だからです。さまざまな施設のお話を聞いても、出生数の減少が進み、分娩の取り扱いが減っていることで助産師らの医療人材も縮小傾向にあります。特に能登地方では都市部と比較すれば人材不足が顕著に表れています。
今回の能登半島地震では、セントラルモニタが使用できなくなったため状況はかなり深刻でした。対応する人手を確保しようとしても、医療従事者も被災している状況です。セントラルモニタリング対応を、応急的にでもいいので早く復旧させることが、被災時の周産期医療チームの強い要望でした。
「emona」はもともと災害時も想定し、開発されていたそうですね。
内田:その通りです。ただ、災害時に使える医療機器、医療システムとは、「普段使い」できるものだと考えています。災害時、緊急時専用に作ってしまうと、いざという時に故障していて使えない、使い方がわからない、リチウムイオンバッテリーが劣化しているなどのリスクがあるためです。また、定期的に保守点検もしなければなりません。
トーイツが大事にしているのは、普段使いできて、持ち出せて、連携できる機器であることです。従来はパソコンに表示用のソフトをインストールして使用しますが、災害時・緊急時の場合はインストール済の専用パソコンが使えなくなる恐れもあります。対して「emona」は一般的なWebブラウザで使用可能なので、ブラウザが動くパソコンであれば、緊急時でも設定するだけで表示できるのが利点です。
有事の際を念頭に置いて開発をしていたので、新井先生からご要望を受けて緊急で「emona」の設置を行い、4営業日というスピード感でセントラルモニタが使える状況を構築できました。
5年間のチャレンジングな開発を経て念願の「emona」リリース
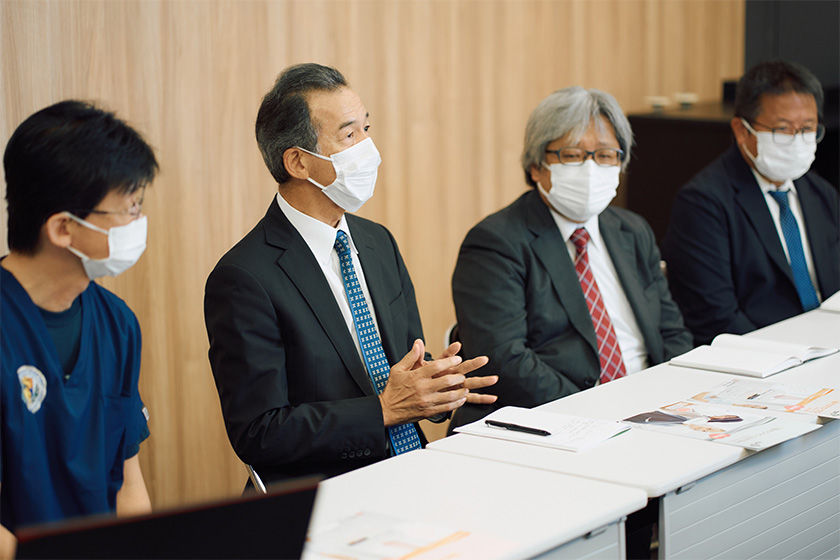
「emona」の開発協力は、とてもチャレンジングだったと語るCSMソリューションの市川さん(左から2人目)。リリースまで約5年という道のりは決して平坦ではなかったようです
写真 落合直哉
「emona」の開発に携わったのが、セイコーグループの関連会社であるCSMソリューションでした。メーカーのトーイツの要望に対してどんな技術提供を実施したのでしょうか。開発時の苦労やリリースまでの挑戦の日々について、市川さん、柴﨑さん、小原さんの3人の担当者に聞きました。
「emona」の開発において、CSMソリューションはどんな技術提供を行ったのでしょうか?
市川:CSMソリューションでは、トーイツ様のコンセプトに沿って、さまざまな製品の開発に協力させていただいています。「emona」ではハードウェアおよびソフトウェアの両面で開発を担いました。技術的にとてもチャレンジングな開発となり、リリースまで辿り着くのにトータルで約5年の歳月がかかりました。
「emona」には複数の製品がありますが、その中でもCSMソリューションが全面的に開発したのが、セントラルモニタの「emona CENTRAL」です。分娩監視装置「emona CTG」については、中に入っているメイン基板、胎児の心拍数と妊婦の陣痛強度、バイタル情報※3を無線で飛ばすソフトウェアを開発しました。また、胎児の心拍数と妊婦の陣痛強度をコードレスで計測できる無線トランスデューサーを開発協力中です。
小原:正直なところ、順調に開発が進んだわけではありませんでした。特に初期では、技術的なトラブルも生じ、開発がなかなかうまく進まないこともありました。こまめに打ち合わせをしながら開発を進めたことを今でもよく覚えています。
※3 バイタル情報:脈拍、呼吸、体温、血圧など患者の生命徴候に関する情報

営業担当として、「emona」の開発においてトーイツとこまめな連携を意識したというCSMソリューションの小原さん。両社の意見交換のパイプ役に徹しました
写真 落合直哉
初期には技術的なトラブルも発生したとのことですが、「emona」開発において技術的に難しい点はどんなところでしたか?
柴﨑:技術的要素に関して個別にさまざまな事前調査を実施したので、1つひとつの要素自体は問題なく機能していました。しかし、統合型のシステムの開発過程においては、要素同士が上手く嚙み合わず、それぞれの機能が正常に作動しない事態が発生しました。その結果として、例えば心拍数の表示に遅延が発生してしまうと、正確なモニタリングができません。開発の佳境の段階で判明したこともあり、全てのパフォーマンスを見直して、CPU※4の割り当ての調整などを行い、作り上げた点にもっとも苦労しました。
また、クラウドのインフラと連携した際に、社内の開発環境でテストして想定していた動きをしないこともありました。また、通信が途切れることも想定に入れなければならないので、後から飛んでくるデータを受け取った時に、空白の部分を埋める変わった動きをしなければなりません。
そうした技術的課題を解決したうえで、救急車に「emona」が乗った時にどのような挙動をするか、テストをしました。ある県で行ったテストでは、山中を車で走り、あるクリニックから総合病院に移動した時を想定してテストし、問題がないことを確認できました。
※4 CPU:Central Processing Unit/中央演算処理装置。データの演算やコンピュータ内の装置の制御などを行う装置

開発の佳境の段階で懸念事項が発生するなど、「emona」の開発は一筋縄にはいかなかったと語るCSMソリューションの柴﨑さん。テストで問題がなかった際はホッと胸をなでおろしたそうです
写真 落合直哉
「emona」が今後の医療界にもたらす可能性とは
新井先生は、この度の災害対応と「emona」を振り返っていかがでしたか?
新井:現在、世界中のどこでも分娩は必要不可欠であるというのが一般的な認識となっています。「スフィアハンドブック(スフィア協会が発行する人道援助の最低基準の教科書)」にも記載があり、そこでは被災地の要望に従い、生命を維持するため、あるいは周産期ケアを実施するための人道支援を行わなければいけない旨が明記されています。
その観点から振り返っても、「emona」を利用することで私たちが被災時でもいち早く平時に近い対応を実現できたことは、「能登のお産を守るうえで大切な支援」でした。ポータブルで使いやすく、クラウドでの保存も可能です。そうした充実の機能が平時から当たり前に使えているため、災害時にもハード機器の破損を気にしなくていいのは大きな利点と言えます。今でも「emona」がフル稼働する状況が続いています。
周産期医療の継続は、今後、全国でより大きな問題になるでしょう。人の住むところには必ず妊婦さんがいて、分娩があります。人手不足の解消は一朝一夕には進まない中で、「emona」のようなシステムが非常に重要です。人手不足はどのエリアでも顕著になってきているので、すでにマンパワーだけに頼ることは、時代遅れとなりつつあります。
今回の能登地方での「emona」というテクノロジーを活用した災害時対応を1つの成功例として、全国に普及させていきたいです。それが実現できれば、私たちの辛い経験も知見として活かされるので、周産期医療の発展に向け励みになると考えています。

人手に頼った現状から、テクノロジーを活用した発展的な医療を提供できる時代へ。取り組みの成功事例として能登半島地震の辛い経験が活かされることを新井先生は願っていました
写真 落合直哉
おすすめの記事
Pick Up Contents
合わせて読みたい関連記事
About
サステナブル・ストーリーとは、持続可能な社会に向けて、
セイコーだからできるサステナブルな活動を発信していく
Webメディアです。